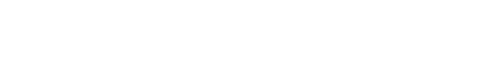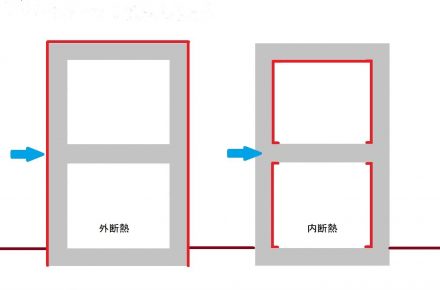組積工事:充填コンクリート打設

前回の記事ではRM造の組積工事の将に組積作業に付いて書きましたが、今日は目出度くも組積工事が終わった後を書いて行こうと思います。
目出度くブロックを一層分積み終わっても壁の部分ダケでしか無いので天井部分(上の階の床部分)は型枠を組んで配筋をしなければなりません。流石にココではブロックを使う訳は行かないのですが、“デッキ”なる建材を使えばこの課程はカナリ捗りますが、今回はその辺りの説明は省きます。
それでこの工法(RM工法)で厄介なのは充填コンクリートの打設です。ブロック内は<スランプ値23cm>と言う通常のRC造では考えられない位のシャブシャブなコンクリートをブロック内に打設致します。これはブロック内に満遍なくコンクリートを充填させる為です。前回の記事に書いた様にこの時に縦筋を挿して行くと言う行程がございます。
そして適切な時間を(1時間程度)充分に掛けて2回り程で完了させます。因みに、壁への充填コンクリート打設は最上部のブロックの1段下位迄です。その後スランプ値を変えたコンクリートを床部分に打設致します。
積み込んだブロックの最下部付近や開口部付近に充填コンクリートがシッカリと回らない(要はブロックの中にコンクリートがチャンと充填されない)とブロック内にジャンカが発生致します。これは大袈裟に言うと建物の強度不足や雨漏りの大きな原因になります。
通常のRC造だとコンクリートの打設後は型枠を外す(脱枠)のでジャンカ等の不具合は目視出来るのでその改善策も考えられるのですが、RM造の場合は脱枠工程が無いので、事故が起きる迄不具合が解らないままなのです。恐ろしいですわ。RM造ブロック自体は単体でもカナリの強度を持たせているので構造的にはそんなに(どんなに?)心配する事は無いと思うのですが、ブロック内にコンクリートがシッカリと充填されて居ないと雨漏りは必至です。はい私が事ある毎にRM造の雨仕舞の脆弱性を訴えている原因はここにあるのでした。
コンクリート打設に慣れた作業員でも流石に<スランプ値23cm>のコンクリート打設は慣れて無いと思います。シャブシャブなコンクリート故に打設時に骨材が不均等にならない様にキッチリとバイブレーションを掛けるのですがこれも掛け過ぎると“過ぎたるは及ばざるが如し”になりますし、打設時間が遅いと1回り目と2回り目のコンクリートに“コールドジョイント”が発生致します。また、早いと打設時のコンクリートの側圧で折角綺麗に積んだブロックにズレが生じてしまいます。
はい、実際カナリ神経を使う作業(コンクリート打設作業)となります。
また、どんな腕の良い作業員でも配筋計画やコンクリート配合計画が適切で無いと、もう腕ではカバー出来ないんで、RM造の構造計算はRM造に慣れた構造計算事務所にさせないと豪い目に遭います。って遭いました、私、豪い目に。「RM造建物の構造設計は慣れている」と言う触れ込みでしたが、もう配筋計画やコンクリート配合計画が素人並でコンクリートプラントや行政の建築科の担当者に笑われるレベルでした。あっ、また愚痴ってもうた。この辺りは以前にも書きましたよね。
RM造のコンクリート打設作業は事程左様に大変です。適切な配筋計画やコンクリート配合計画があった上に、充填コンクリート打設作業のノウハウと経験がものを言う世界だと思います。
って事でだいぶ端折ったコンクリート打設工程の説明でしたが本日はココ迄
Sean Y.